令和5年5月27日、茨城県石岡市立の小学校において、6年生の女子児童数人が内科検診をスムーズに受けられるようにとの理由で、担任教諭から上半身の下着を脱いでおくよう指示される事案が発生しました。
茨城県内小学校で発生した事例の概要
事案の詳細
この事案では、以下のような経緯で問題が発生しました:
- 昼休みに女児が保健室に集められ、担任教諭から事前に上半身の下着を脱ぐよう指示された
- ブラジャーと胸パッド付きキャミソールはそのままでよいとの指示があった
- 女児数人が白色の体操服1枚で教室に戻り、5時間目の授業を受けた
- 内科検診を受けるまでの間、恥ずかしがったり男児から冷やかされたりする女児がいた
本来は、女児が内科検診を受ける順番になってから保健室で着替えて検診会場に向かうことになっていましたが、担任教諭が手順を誤ったとされています。

関係者の反応と学校の対応
この事案に対し、6年の女児の保護者は「子供を守るはずの学校側が無神経な対応だ」と憤りを表明しました。学校側は「児童への配慮が足りず、たいへん申し訳ない」と陳謝し、校長は「教職員に通知内容や検診の手順の順守を徹底させる」と述べています。
この事案の問題点
主な問題点
- 児童のプライバシーと尊厳への配慮不足
- 適切な手順の無視
- 児童の心理的負担への認識不足
- 文部科学省通知の理解・実行不足
文部科学省の取り組みと新たな通知
文部科学省は、学校の健康診断等を巡り、令和5年1月に児童生徒のプライバシーに配慮するよう都道府県の教育委員会などに通知を発出しました。さらに、令和6年1月22日には「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備について」という新たな通知を発出しています。
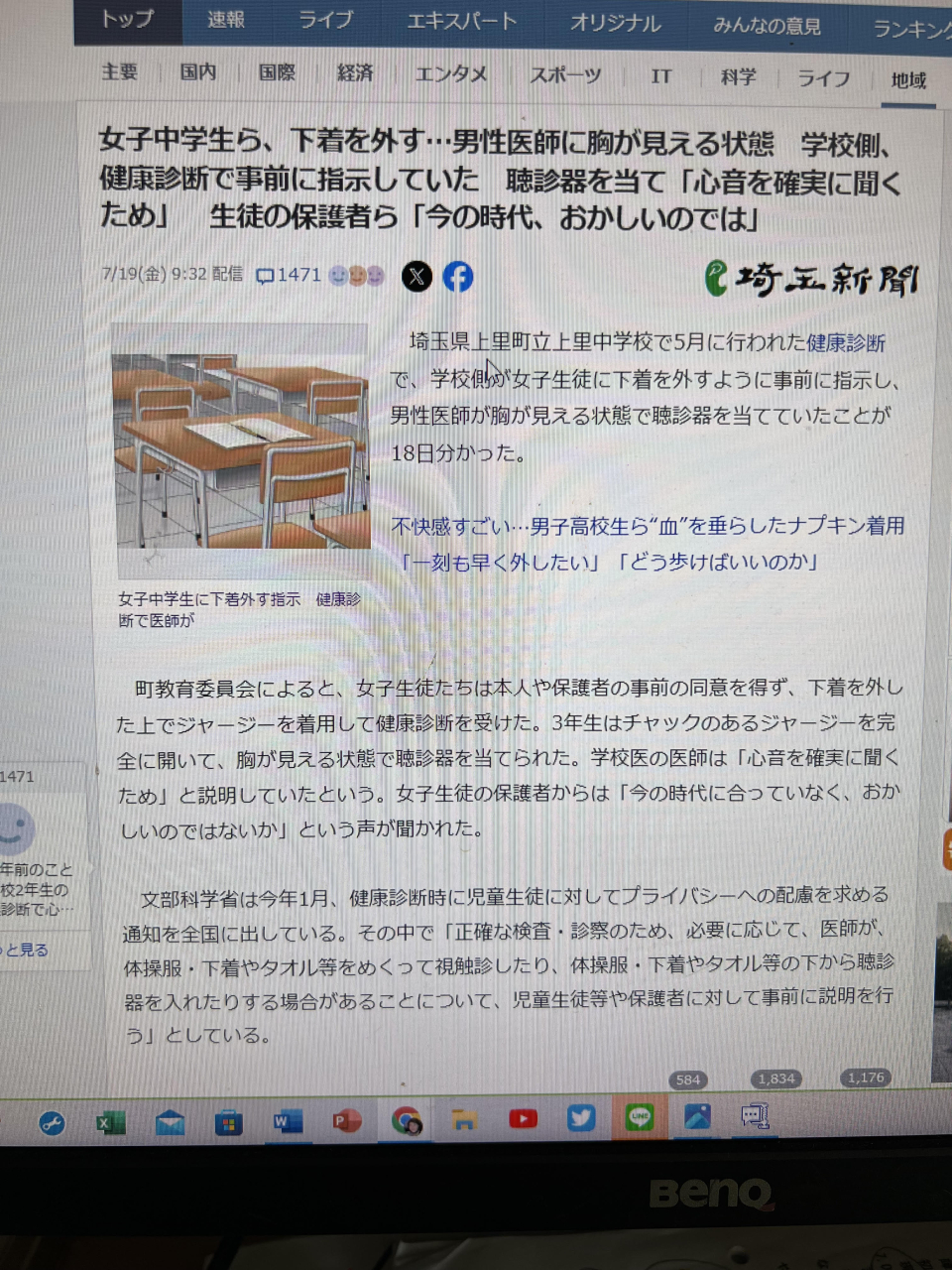
文部科学省通知の主な内容
通知では、診察時は支障のない範囲で、原則体操服や下着を着用するなど児童生徒の心情に配慮する必要があると指摘しています。具体的な対応について以下が示されています:
| 配慮事項 | 具体的な対応 |
|---|---|
| 男女別実施 | 男女別に検査・診察を行う |
| プライバシー保護 | 児童生徒の体が周囲から見えないよう、囲いやカーテンなどで個別の検査・診察スペースを用意 |
| 着衣での実施 | 診察時は支障のない範囲で、原則体操服や下着を着用 |
| 心情への配慮 | 児童生徒の心情に十分配慮した環境整備 |
適切な健康診断実施のためのガイドライン

環境整備の具体例
適切な健康診断を実施するためには、以下のような環境整備が必要です:
- 個別検査スペースの確保
パーテーションやカーテンを使用し、他の児童から見えない空間を作る - 適切な着衣での実施
上半身の検査においても、体操服やタンクトップの着用を基本とする - 同性スタッフの配置
特に思春期の児童に対しては、同性の教職員や学校医による対応を心がける - 事前説明の充実
検査内容や方法について、児童や保護者に事前に十分な説明を行う
教職員研修の重要性
適切な健康診断実施のためには、教職員への研修も不可欠です。特に以下の点について理解を深める必要があります:
- 児童の人権とプライバシーの尊重
- 発達段階に応じた配慮の必要性
- 文部科学省通知の正確な理解と実践
- 緊急時における適切な対応方法

保護者・地域との連携
学校健康診断の改善には、保護者や地域社会との連携も重要です。以下のような取り組みが効果的です:
情報共有と透明性の確保
学校は健康診断の実施方法について、保護者に対して事前に詳細な説明を行い、理解と協力を求めることが重要です。また、実施後には結果だけでなく、実施過程についても適切に報告する体制を整える必要があります。
相談体制の整備
児童が健康診断について不安や疑問を感じた場合に、気軽に相談できる体制を整備することも重要です。養護教諭やスクールカウンセラーなど、専門職との連携を強化し、児童の心のケアに努める必要があります。
今後の課題と展望

制度的改善の必要性
今回の事例を踏まえ、以下のような制度的改善が求められています:
- 統一ガイドラインの策定
全国統一の詳細なガイドラインを策定し、地域や学校による格差を解消する - 定期的な研修制度の確立
教職員に対する定期的な研修制度を確立し、知識の更新と意識の向上を図る - 第三者評価システムの導入
外部専門家による評価システムを導入し、客観的な視点からの改善を促進する
デジタル技術の活用
今後は、デジタル技術を活用した健康診断の効率化とプライバシー保護の両立も検討課題となります。タブレット端末を使用した問診システムや、AIを活用した診断支援システムなど、新しい技術の導入により、より適切で効率的な健康診断の実現が期待されます。
まとめ
茨城県内の小学校で発生した事例は、学校健康診断における配慮不足が児童に与える影響の深刻さを改めて浮き彫りにしました。この事例から学ぶべき最も重要な点は、児童のプライバシーと尊厳を最優先に考えた健康診断の実施が不可欠であるということです。
文部科学省の新しい通知は、このような問題の再発防止に向けた重要な指針となります。しかし、通知の存在だけでは不十分であり、すべての教育現場でその内容が正しく理解され、適切に実践されることが重要です。
重要なポイント
- 児童のプライバシーと心情への最大限の配慮
- 文部科学省通知の正確な理解と実践
- 教職員の継続的な研修と意識向上
- 保護者・地域との連携強化
- 制度的改善と新技術の活用
すべての子どもたちが安心して健康診断を受けられる環境を整備することは、学校教育における基本的な責務です。今回の事例を教訓として、より良い学校健康診断の実現に向けて、関係者一同が連携して取り組んでいくことが求められています。
子どもたちの健康と幸福を守るためには、単に身体的な健康状態を把握するだけでなく、検査過程において心理的な安全性も確保することが不可欠です。このことを改めて認識し、すべての学校で適切な健康診断が実施されることを強く願います。

コメント